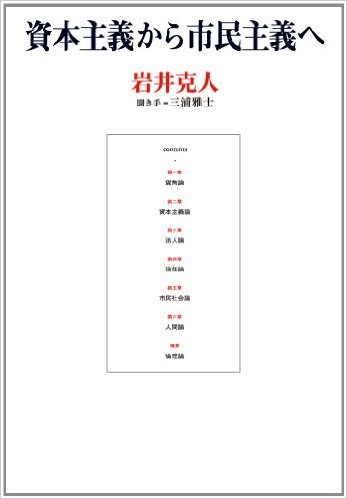
今年初めて「良書」の読書日記でございます。『資本主義から市民主義へ』(岩井克人、聞き手三浦雅士、ちくま学芸文庫、2014年4月。原題『資本主義から市民主義へ 貨幣論・資本主義論・法人論・信任論・市民社会論・人間論』新書館、2006年8月)
昨年来、アカデミズムの悪口ばかり言っているわたしですが、(とはいえそんな中でもご厚誼をいただける大学の先生というのは2−3いらっしゃるのですが) 「この人の知性は一回りも二回りも大きい」と感じさせる方がいらっしゃいます。
岩井克人氏(東大名誉教授、国際基督教大学客員教授)の『会社はこれからどうなるのか』『会社はだれのものか』は、2006年のわたしの超・短命だったビジネススクール時代、周囲がいまだ「株主主権論」にかぶれていた中、バイブルというか「お守り」のようなものでした。
ただしわたし自身は「経済頭」ではないため岩井氏の研究全体を理解するすべもなく。今も「単なるファン」です。昨年の同氏の『経済学の宇宙』も読むには読んだが、到底評価などできる器ではございません。ので、読書日記もレビューも上げることができずじまいでした。
昨年もう1冊手にとった本書『資本主義から市民主義へ』は、岩井氏の「倫理」についての考え方がわかる好著です。2006年時点で既にここに至っていたかと感銘を受けます。
もちろん「倫理畑」の方々からは異論もございましょうが、わたしの「趣味」とお許しをいただいて、本書の感銘を受けたところをご紹介したいと思います。
今回は、ワード16ページの長さになりました。要約ではなく引用です(わたしが意味がわかっていないところが多いため)。太字部分はわたしが勝手に主観的にだいじだと思ったところを太字化してあります。
****
岩井:法人の成立については、ぼくは、間主観性、というよりも社会的承認が不可欠であることを強調しています。現在のアメリカの主流派経済学の連中や、それに影響を受けた法学者たちは、法人とはたんなる契約にすぎないと言っています。でも、たとえばいまAさんとぼくが法人をつくりたいと思って、二人のあいだでどんなに詳細な契約書を書いたとしても、ほかの人間が、Aさんとぼくがつくった団体をAさんやぼくとは独立の主体であると認めてくれなければ、法人としての機能を果たすことはできません。ほかの人間と契約を結べないし、独自にモノを所有することもできない。つまり、法人という制度にかんしては、他人による承認、もっと一般的には社会的な承認が絶対に必要なのですね。もちろん、「人の噂も七十五日」ではないけれど、社会的な承認などというのは移ろいやすいので、それを国家が法律化して、制度として安定させたものが、法人です。(p.124)
岩井:じつは、会社論の次のテーマとして、国家論のほかに倫理論を考えていますが、その出発点として、信任に関する理論を展開したいと思っています。(p.128)
じつは「資本主義社会は倫理性を絶対に必要とする」というのが、ぼくの主張です。しかも、まさにそれが契約関係によって成立する社会であることによって倫理性が要請されるということなのです。(p.129)
岩井:じつは、ぼくは最近、いま述べたことを一歩進めて、もっとも根源的な人間の関係は信任関係であって、契約関係とはその派生的な形態であると見なすようになっています。そして、そこから出発して、市民社会というものを考え直してみたいと思っているのです。そのなかで、倫理性という問題について考え始めているのです。(p.131)
だいぶ脱線しました。…先ほどから宿題であった倫理の問題に戻ります。端的に言ってしまうと、倫理とは、人間が死ぬ存在であることと本質的にかかわっていると思っています。なぜなら、人間が永遠に生きられるとすると、現在何か悪いことをやっても、将来かならず相手に対して償いをすることが可能になるからです。それは、すべてを、法律的な権利義務の関係、いや、もっと正確には、経済的な貸し借り関係に還元してしまうことになるのです。そこでは、ほんとうの意味での倫理性は必要でなくなってしまう。だが、人間は有限な存在です。だから、自分のおこなった行為に対して、どのようにしても償いや返済ができない可能性がある。そこではじめて、本来的な意味での主体的な責任という問題が生まれてくるのです。それが究極の意味での倫理の問題だと思うのです。(pp.131-132)
―(???)この論理構築はよくわからない…わからないなりにおもしろかったので抽出させていただきました。
(三浦)デ・ファクト・スタンダードの問題がある場合、倫理はどういうかたちで成立するのか。倫理はなんらかの定点を必要とするのに、地面がぐにゃぐにゃの状態と言っていいわけです。カントの倫理を皮肉ったのはシラーでしたよね。自己一身の責任においてというのでは、結局、あらゆる善行は趣味の問題になってしまうではないか、と。倫理はどうしても大文字にならざるをえない。
岩井 大文字かどうかはわかりませんが、人間には、たとえだれも見ていなくても、神さえ見ていなくても、主体として一方的に責任を引き受けなければならない場面なり瞬間がある。(pp.135-136)
岩井 ちょっと前ですが、猫も杓子も「他者」「他者」といっていた時期がありました。「他者」との出会いを求めて、ノコノコと外国に行ったりしてね。でも、先ほど、人間とは、言語を語り、法にしたがい、貨幣を使って、はじめて人間となる存在であると言ったわけですが、その人間にとっていちばん本質的なことは、そのような意味で人間をまさに人間とさせる言語・法・貨幣、とくに言語が、人間にとってはまったくの外部の存在であるということなのです。
(三浦)われわれがもっとも内部だと思っているものが、じつはもっとも外部だということ。
岩井 まさにそうです。そのことを認識することがすべての倫理の出発点だと思うのです。まさにこれは自己疎外論の正反対です。外部の他者との出会いなど、些末な問題だとは言いませんが、二次的な問題です。人間にとっての最大の他者とは、まさに人間にとって最大の内部である言語であるのです。人間はまさに言語で思考し、言語を介して他人とコミュニケートするわけで、言語とは人間の思考そのもの、人間のコミュニケーションそのものなのですが、その言語が人間にとって、もっとも外部の存在であるということなのです。事実、個々の人間はかならず死にますが、言語は個人の死にかかわりなく生きつづけていくわけです。
(三浦)まったくそうです。個別性自体のなかに彼岸があるということです。岩井さんの考え方でいくと、自己は最初から共同性のなかでしか成立しない。
岩井 共同性と言ってもそれは、言語という外部を媒介とした共同性という意味です。だから連帯していて仲良しというわけじゃない。
(三浦)もちろんそうじゃない。でも、言語で考えるというときには、自分ひとりで考えていたとしても、それは共同性において考えているわけですよ。
岩井 共同性といわれると、抵抗を感じるんです。
(三浦)なんといえばいいんでしょう。
岩井 ぼくは超越性だと思っているんです。
(このあと三浦の反論。「ほんとうに19世紀的なヒューマニズムでしかない」)
岩井 ぼくもわからない。ただ、最終的にはカントのいう意味での倫理になるのではないかとは考えています。(pp.137-139)
岩井 たしかに労働価値もない。主体もない。そこで、ぼく自身は、ある意味で非常に常識的なところに戻っていく。カント的な啓蒙思想です。ぼく自身はこれまでずっと資本主義について思考してきました。その資本主義とは、まさに差異性から利潤を生み出すというもっとも形式的なシステムであり、それゆえにもっとも普遍的なシステムです。だから、必然的にグローバル化してしまった。そして、それを超えるシステムはありえません。では、そのような普遍性をもった資本主義に対抗しうる何かがあるとしたら、それも同じように形式的な原理でなければならない。具体的には、カント的な定言命題による倫理性であり、それを基礎にしたグローバルな市民社会といったものになるのでしょうか。カントの定言命題とは、それが普遍的な法則となるような格率にしたがって行為せよというものですから、完全に普遍化しうる純粋に形式的な命題です。これ以外にはないんじゃないかと思います。たとえばローカルな共同性を強調するコミュニタリアン的な論理だけでは、まったく勝ち目はありません。
(略)
(三浦)岩井さんは、カント主義はヒューマニズムだと思っていないんですか。
岩井 思っていません。だってカントの定言命題の対象は、人間でなくてもいいんですから、理性をもっている存在すべてに当てはまる方法なんです。理性をもっている存在ならば、お互いをたんに手段としてではなく、必然的に目的として扱うはずだ、と考える。(pp.139-141)
岩井 いま理性と言いましたけれど、その理性の意味に二つあることが重要です。ひとつは、なんらかの公理から出発し、一歩一歩論理を積み重ねて真理に達するための理性。これが通常の意味での理性です。もうひとつは、ゲーデル問題に関連しますが、この世の中には、あらかじめ与えられた公理とは独立に、自己循環論法によってそれ自体で完結している真理がある。それは、まさにとびとびに存在する真理です。こういう真理は、まさに歴史的に発見されなければなりませんが、そういう真理を見たとたんに、それを真理として認知できる理性です。(pp..141-142)
岩井 人間はそれに行き当たると、それが真理だとわかる。ハイエクは、ヒュームの偉いところは、この第二の理性について思考したことであるというのです。いずれにせよ、こういう真理は進化論的にしか行き当たらないわけであって、そこに、歴史の本質的な意味での不可逆性があるのじゃないでしょうか。
―このあたりわたしの「趣味」で太字部分が増えてしまいましたが、わたしは勝手に、「承認」というものは、歴史を不可逆的に変える真理の発見の1つなのではないか、と思っているわけです。
自分のコメントも勝手に太字にしてしまいました^^
岩井 ちょっと話がずれますが、同じようなことが倫理についても言えます。カントの道徳論に、すべての人間をたんに手段としてだけでなく同時に目的として扱えという定言命題がありますね。これもよく見ると自己循環論法になっています。理性的存在がお互いに理性的存在であることを承認しあうわけですから。そして、そのような相互承認を実定化すると基本的人権になるわけです。その意味で、基本的人権とは普遍的な概念ではあるけれども、同時に歴史的に発見されたものでもあるというわけです。これは非常に啓蒙主義的な考え方に近い。
少なくとも倫理にかんして残るものは、案外、常識的なものでしょう。(pp.143-144)
岩井 言語や法や貨幣はデ・ファクト・スタンダードですが、それをぼくは空虚とは言わない。それは、現実に個々の人間のあいだを流通していく社会的実体です。実体的な根拠がないことと、空虚であるということとは、まったく別です。そして同じことは、カント的な意味での倫理についても言える。それも自己循環論法によって成立するひとつの命題です。そして、空虚ではない。実際に、基本的人権というようなかたちで社会的な実体性をもつことができる。
いずれにせよ、言語・法・貨幣、さらにそれとは別のカテゴリーですけれど、定言命題としての倫理―これらが、まさに自己循環論法の産物であるということ、つまり実体的な根拠をもっていないということに、究極的には人間の人間としての自由の拠り所があるし、人間にとっての救いがあると思っています。自己循環論法であるからこそ、遺伝子情報の制約からも、人間理性の限界からも自由になれるのです。その意味で、言語・法・貨幣、そして倫理、とりわけそれらすべての基礎にある言語のなかに、もっとも根源的な真理が隠されているわけです。無根拠だから空虚なのではありません。無根拠だから真理を見出していく無限の潜在力にあふれているのです。(pp.144-145)
岩井 ええ、信任関係を生み出す。一方が他方を一方的に信頼することによってしか成立しない関係を生み出す。この関係が成立するためには、信頼を受けた側は、自己利益を押さえて行動しなければならない。つまり、倫理性を絶対に要請してしまう。こうして資本主義のまさに中核に信任関係、倫理が登場するわけです。(p.165)
(三浦)岩井さんは『会社はだれのものか』の最後で、ケインズとフロイトの関係にちょっとふれていますが、たとえば、ご存知のように、ラカンがヘーゲルとフロイトを結びつけるとき、ひとつのポイントにしたのがアウフヘーベンという言葉ですよね。『エクリ』のなかに、哲学者のイポリットにフロイトの「否定」という論文について評釈させるところがありますが、そこでポイントになるのがアウフヘーベンという言葉で、要するにフロイトのいう否定し抑圧するということの実質はアウフヘーベンと同じだということですね。(p.174)
(三浦)ヘーゲルがアウフヘーベンという言葉を用いたのは概念の働きを説明するところにおいてですが、ヘーゲルにおける概念、概念化作用というのは、じつはそのまま否定と抑圧のことなんだと言ってもいいほどだと思います。定義が否定によって成り立つように、概念も否定によって成り立つということは古くから言われてきたことですが、ヘーゲルはそこに抑圧の要素をも見た。つまり持続の要素、否定しても無くならないものがあるということを見た。つまり二重性です。ヘーゲルはそれを表現するためにアウフヘーベンという言葉をもってきたわけです。
ヘーゲルの概念の概念についての研究が必要だと言ったのはガダマーですが、ヘーゲルの概念の概念には、それまでは知性とか悟性とかいうレベルで論じられていた概念というものを生命現象一般にまで強引に拡げてしまったところがあって、たとえば動物の概念化作用というのは食べるということそのもの、生殖ということそのものだというわけですね。
(pp.175-176)
岩井 ぼくはカントの『実践理性批判』や『道徳の形而上学』は、それが純粋に抽象的、形式的な原理として倫理を提示しているところがおもしろいと思っています。なぜならば、資本主義というのも、基本的に形式にすぎません。価値形態論とは、商品と貨幣のあいだのほんとうに形式的な関係です。純粋形式ですよ。ぼくはこれから資本主義論を超えたものとしての市民社会論をやろうと思っているんですが、資本主義とは純粋に形式的なシステムだから、ここまでグローバル化したわけです。その資本主義を超える人間と人間の関係として市民社会が可能になるためには、それは少なくとも資本主義と同じ程度には形式的でなければならない。そこで、やっぱりカント的な理論がその核心になるはずだということです。その基礎として、現在、法人論から出発して、信任論について考えているわけです。(pp.205-206)
岩井 うん。だけど、カントが言う、仮言命題にもとづく倫理は、真の意味での倫理ではない、定言命題として定式化される倫理のみが倫理であるという考え方とおもしろいほど適切に関連してくるんですよ。なぜならば、定言命題とは自己循環論法なんですよ。カントの倫理論がおもしろく、そして深いのは、それが自己循環論法になっているということなんです。
仮言命題的な倫理というのは、個人の幸福であれ、社会の利益であれ、なんらかの効用や目的を達成するための手段として定式化されている。約束を破ると人からの信用を失って、結局は損をするから約束を破ってはいけないというたぐいの理論です。これに対して、定言命題というのは、外部からのなんの根拠づけも必要としない。それ自体を目的とする行動規範です。つまり、それが同時にすべての人間にとっての行動規範となることをあなたが望む行動規範にもとづいて行動せよ、というわけです。約束を破ることは、それ自体でいけない。他の人が約束を破らないとき自分だけ約束を破るのは個人にとっては得であるかもしれない。だが、すべての人が約束を破ることを行動規範にすれば、約束という制度そのものが不可能になるから、約束は破ってはいけないというわけです。これはほとんど数学のように形式的な命題です。
言ってみれば、仮言命題は社会主義的で、定言命題は徹底的に反社会主義的です。個人の行動を社会全体の利益の名において制約する仮言命題的な倫理の極致が、社会主義だからです。カントは、外から与えられたなんらかの目的から導かれる倫理というものを全否定する。それ自体が目的である行動規範こそ倫理であるというのは、倫理がまさに自己循環論法であるということです。カントを語る多くの学者はこのことの重要性を理解していないと思うのです。倫理というのは自己循環だということを……(pp.206-207)
岩井 そうなんですけど、重要なことは、カントの理論は権利論として理解できるということです。たんなるシニシズムではなくてね。
政治哲学や倫理学で、昔から効用主義と権利主義のあいだで論争がありますよね。たとえば、基本的人権や私有財産権のような人間がもつさまざまな権利に関して、その権利を絶対多数の絶対幸福を実現するための手段としてみるのか、それともそれ自体が守られるべき目的とみるのかという論争です。カントはもちろん、権利論者です。ただ、同時に、カントは通常の意味での自然法論者でもありません。
たとえば、基本的人権とは、すべての人間は他人の手段としてのみ扱われてはならないという倫理規範を法律化したものです。その出発点は、理性的な存在同士がお互いを理性的な存在として認めあうことです。理性的な存在とは自分で自分の目的を設定できる存在であり、お互いが理性的な存在であることを認めあうことは、お互いがお互いを目的それ自体として認めることになるわけです。そのような相互承認がないかぎり、基本的人権などは存在しない。事実、基本的人権なんて昔は存在しなかった。たとえばギリシア時代には、基本的人権なんて、お互いにお互いを英雄として認めあう英雄しかもっていなかった。でもそれが、権利への闘争の長い道のりを経て近代になって確立し、現代においては、少なくとも先進国の人間はあたかも基本的人権が自分の体の一部でもあるかのように振る舞っています。
そもそも基本的人権というのは物理的にあるわけではない。相互承認を法的に権利化、いや実体化したにすぎない。けれど、たとえばアメリカ人なんか、自分の基本的人権を鎧のように着て世界中を闊歩している。(pp.208-209)
岩井 どこにも実体はない。言語だって、言葉に意味があると言っても、後期ヴィトゲンシュタインの先ほどの言葉を敷衍すると、それは意味があるものとして使われているから意味があるにすぎないわけですね。完全に自己循環論法です。法も、人々がそれに対して法としてしたがうから、法が法として効果をもつ。これも自己循環論法です。カントの倫理にしても、いま説明したように、構造はだいぶ複雑になるけれど、そうなんです。人間社会には、物理的な実体とは違う社会的な実体があるわけです。しかもその社会的実体を媒介にして、はじめて人間は人間となる。その社会的実体は、自己循環論法の産物ですから、物理的には何モノでもないのに、人間にとってはものすごい実体性をもつ存在となっているわけです。(pp.209-210)
岩井 そうですね。貨幣論では、貨幣は自己循環論法の産物であり、実体的根拠はないと言っているわけですし、資本主義論だって、価値体系の異なる二つのシステムを媒介すると、無から有が生まれてくるように、利潤が生まれてくると言っているわけですしね。こういう貨幣の論理、資本主義の論理が、現在、グローバル通貨、グローバル資本主義というかたちで、世界を覆いつくしてしまったわけです。
このような動きに対して、みんないろいろ抵抗しようとしています。ただ、その抵抗の方法が、コミュニタリアニズムであったり、地域通貨であったりしているかぎり、絶対に勝てない。なぜならば、貨幣も資本主義も、純粋に形式的な論理によって動いているからです。だから、グローバル化しうるのです。それに対して、なんらかの意味で実体的な根拠を示して対抗しようとしても、それはローカルな効果しかもてない。それに対して唯一勝てるのは―べつに勝たなくてもいいんだけれど―、やはり、純粋に形式的な論理、いや倫理なのですね。その点で、カントの倫理論が意味をもってくる。なぜならば、それはまったくの自己循環論法として定式化されているからです。それが、貨幣と資本主義のグローバル性・普遍性に対抗しうるだけのグローバル性・普遍性をもった、唯一の対抗原理でありうると思っているのです。(p.215)
岩井 ふつう、自己循環論法というと、自己矛盾だとかアンチノミーだとか言って話を終わりにしちゃうんだけど、じつはそれこそが真実であると。それこそが貨幣である、それこそが言語である、それこそが権利である、とういことなのです。
(三浦)ヘーゲルに言わせれば、それこそが精神だってことになるでしょうね。
岩井 結局、人間の社会とは、その人間が作り出した数学という純粋論理の世界ですら、進化論的な意味での発展をしているということですね。ゲーデルの定理は、構築された真理ではないから、たまたま発見されるよりほかないのです。もちろん一度発見されると、だれもがその正しさを認めざるをえないのですが、発見されるまでは真理としても存在していなかったわけです。それがたまたま発見されると、それ以前の状態には戻れなくなるわけですよ。一種の歴史的な不可逆性がここにある。つまり、ゲーデルの定理が発見されると、それによって世の中の複雑性が増してくる。エントロピー増大の法則が打ち破られてしまうのです。たしかに、これがヘーゲルの言う精神かもしれませんね。(pp.219-220)
岩井 さっきの、カントの定言命題は真理か思想か、という問題については、こう言ったらいいでしょうかね。いまはまだ思想なんですが、いつかは真理となる思想である。そして、カントの倫理がたんなる思想ではなく、真理となった社会―これが、市民社会であるということです。
たとえば、市民社会の最低限の条件は基本的人権の確保ですが、基本的人権とは、カントの定言命題の法律的な表現にほかなりません。現代でも、まだ国によって違いがある。基本的人権が守られていない国や社会は、まだたくさんある。しかし、ある歴史段階になって、その国が市民的に成熟してくると、基本的人権が法律的に守られるようになり、そうすると、その国のなかでは、人間が基本的人権をもつということが疑いのない真理になるんだと思う。先ほど言ったように、どの人間も基本的人権をあたかも体の一部であるかのように所有することになるわけです。
カント的な意味での定言命題的な倫理は、だからいまは思想にすぎないけれど、形式的には自己循環論法になっていますから、そこにうまく法律、場合によっては人々の常識がはまりこんで動き出すと、これは真理になる。そう思いますね。(pp.223-224)
岩井 ぼくはいま市民社会論に足を突っ込み始めているのですが、そのためにはまず最初に資本主義の枠組みのなか、私的所有権の世界のなかでどれだけ言えるのかを確定する必要があると思って、それで、会社の二重構造論から、株主主権論を批判し、経営者について信任論を展開し、ポスト産業資本主義における利潤の源泉がヒトであるという議論を提示してみたわけです。このような議論は、すべて資本主義の枠組みのなかでここまでは言えるということをやっているわけです。
たとえば、ポスト産業資本主義におけるヒトの役割の重要性を強調している場合でも、それは、心優しく従業員のためを思うヒューマニスティックな経営者がいいんだというような議論を展開しているわけではありません。あくまでも、ヒトを重視しなければ、会社はポスト産業資本主義のなかの競争で負けてしまうと言っているだけです。
ただ、一歩、社会的責任論に足を踏み入れると、単純な私的所有権の枠組みをちょっとはずれてきます。ぼくの市民社会論は市民社会の定義がまだはっきりしていないんだけど、現在のところとりあえず、市民社会とは資本主義にも還元できなければ国家にも還元できない人間と人間の関係である、と定義しています。資本主義的な意味での自己利益を追求する以上の、何か別の目的をもって行動し、国家の一員として当然果たさなければならない責任以上の責任を感じて行動する人間の社会だということです。それが社会的責任だと思います。(pp.225-226)
岩井 そうかなあ、やはりぼくは社会主義者ではないですよ。あのとき、ぼくは社会主義者ではないが、市民社会主義者であると返事すればよかったと、いまになって思います(笑)。要するに、そのなかではお互いがお互いに対して、資本主義的な自己利益、自己責任という意味での責任にも、国家における法的な義務としての責任にも還元できない責任を考え始める市民社会ですね。
市民社会というのは一貫して「国家および資本主義を超える何か」という存在でしたし、これからもそうでありつづけるはずです。たとえば、市民社会で障害者の権利についての主張が始まる。だが、それが人々の政治的なコンセンサスにまで高まると、法律化されて国家の側に吸収されちゃうし、あるいは社会的な責任を果たすべく、NPOとかで活動してうまくいくと、そのうちに採算がとれ始めて資本主義に吸収されたりします。市民社会とは、その意味で、確定した領域をもっているわけではなく、つねに自己の領域をつくりつづけていかなければならないものです。
いずれにせよ、逆説的だけど、国家にしても資本主義にしても、人間がお互いに責任感をもって行動しているような市民社会的な領域の存在を許すだけの余裕がなければ駄目なんです。そして、この領域が増えてくると、たんなる資本主義の単純な私有財産の枠組みにも、国家が定めた法律の枠組みにも入りきらないプラスアルファが、市民だけでなく、会社にも要求されるようになってくる。ここでちょっと私的所有権じゃないところに入っていくんですね。(pp.226-227)
(三浦)そんなことはないでしょう。岩井さんのお話を伺って、カントの歴史的意義がわかったという人もたくさん出てくると思います。とくに思想が真理へと進化するという考え方は画期的ではないでしょうか。
岩井 いろいろな権利が体の一部のように人間に備わってしまうということですね。また、基本的人権とは違ったさまざまな権利もありうる。でも、それらの確立は難しいかもしれませんね。でも、いままで人間としての扱いを十分に受けてこなかった人間がいろいろな権利をもつということは、やはりカントの自己循環論法の領域ですね。お互いの尊厳性を認めあうということが権利というかたちで定着してくるわけです。
(三浦)だけど、繰り返しになって申し訳ないですが、岩井さんの考えが刺激的なのは、つねにすべてが無意味になる地点を含んでいるからです。基本的人権は幻想なんだということも含んでいる。その幻想を受け容れて考えていくことが君たちの自由なんだと言っているように思えますね。
岩井 ただ、ぼくは幻想という言葉は使いたくないんです。幻想じゃないんです、これは。実体なんです。真理なんです。根拠がないということと、幻想であるというのは違うと思うんですよ。だから吉本さんの共同幻想という言葉も、あれは誤解を招きます。やっぱり国家は実体です。権利も実体です。社会的実体。ただその社会的実体は社会との相関関係のうちにしかないということです。そういう意味では、物理的な実体ほどの確実さはありませんけれども、しかしあくまでも実体です。幻想という言葉は、ぼくは批判としてしか使いません。
(三浦)じゃあ、建設的虚構と言えばいいかもしれない。
岩井 そうそう、まさしく建設的虚構です。ほんとうに、良い言葉です。
(三浦)その場合、建設的にウェイトを置くか、虚構にウェイトを置くかで違ってくる。
岩井 小説はフィクションだというけど、そのたんなるフィクションがある意味で現実よりもはるかにリアリティをもつものとして、みんな寝食を忘れて読んでしまうことがあるわけです。そういう作家も読者もいるわけだから、ぼくは建設的という言葉に重きを置きます。(pp.230-231)
岩井 では、このような遺伝決定論の科学的な勝利の結果、人文科学・社会科学は、エドワード・ウィルソンが言うように、すべて生命科学の応用分野に成り下がってしまうのか、というと、じつは、逆転ホームランがある。まさに、すべてを遺伝子に還元しようという動きがあることによって、逆に何が遺伝子に還元できないかが浮き彫りにされることになる。それこそ、言語・法・貨幣の存在なのです。人間が生きている世界のなかには遺伝子に還元できない社会的実体がある。人間の遺伝子をいくら調べても、そのなかに貨幣は明らかに入っていない。法はどうか。もちろん、人間には社会的規範を守るという遺伝子があるということは、最近いろいろな実験によって明らかにされています。したがって、アダム・スミス的な利己的な人間像というのは遺伝的に正しくない。人間には規範を守る遺伝子があるのだ、というわけです。こういう発見は、ぼくは大いに歓迎します。でも、それによって、ことの本質を見失うことになる危険がある。なぜならば、遺伝的な規範意識と法とははっきりと区別すべきだと思うからです。(pp.241-242)
岩井 だが、フリードリッヒ・ハイエクが指摘するには、人間の本能にとっては私的所有権ほど嫌なものはないというのです。
(中略)
狩猟社会では財産は共有、だれが獲物をとってきてもみんなで分ける。そうじゃないと共同体的な社会組織はうまくいかない。その強い連帯意識がいちばん嫌うのはもちろん個人間の能力の差であり、さらには私有財産です。ところがあるとき、どこかの部族が私有財産制を採用し始めた。ユダヤ人かもしれないし、フェニキア人かもしれない。
(三浦)ユダヤとフェニキアは同祖だという説があります。陸の商人と海の商人。
岩井 人間の本能にはまったく反してしまうんだけど、私有財産制という慣習、さらには法制度に行き当たってしまった。突然変異なのか、だれかが理性的に考え出したのかはわからない。そして、人間の連帯意識的な本能に逆らうこの私有財産制を採用した部族なり民族は、その結果、資本主義を発見してしまい、経済的に飛躍的に発展してしまう。それを見て、対抗上、他の部族や民族も、嫌々ながら、私的所有権制度を採用せざるをえなくなった。その最終的な結果が、現在のグローバル資本主義であるというわけです。だから人間は、規範意識は遺伝的にはもっていても、私的所有権制度という法を遺伝的にもっているわけではない。法律は、遺伝に逆らって成立したんです。(pp.242-244)
岩井 こうして言語・法・貨幣を媒介として、人間は初めて抽象的な意味での「人間」として社会を形成することができる。もちろんこれらがなくても共同体はつくれるけれど、それはお互いをよく知りうる範囲に限定されてしまう。人間は、まさに言語・法・貨幣を媒介として、お互いを抽象的な「人間」として認めあうことになり、動物と違う次元の社会性をもつ存在となる。言語・法・貨幣を媒介とすることで社会を形成する生物、それこそが人間の本性なのです。(p.255)
(三浦)(ドーキンスのミームに言及)
岩井 たしかに、僕の理論はそれに近いと思うけれど、自己循環論法としての言語・法・貨幣を媒介した関係として、もっと正確に人間の社会性を規定している。かれらは「文化」とかいう言い方で、曖昧ですね。(p.256)
岩井 言語、法、貨幣では言語がまず根源的 近代に私有財産についての法が確立 ほとんど貨幣の成立と対応関係をもっている(p.257)
岩井 そうです。だから言語・法・貨幣の成立は、同時に「人間」の成立でもある。人間は社会的生物だけれども、言語・法・貨幣を媒介として初めて「人間」として社会をかたちづくることができる。生活をともにしたことのない相手ともコミュニケーションでき、腕力のかなわない相手とも契約が結べ、自分の欲しいモノをもっていない相手とも交換できる。人間社会というのは、個々の人間の集まりじゃなくて、抽象的な意味での人間同士の関係なのです。(p.259)
岩井 ええ。典型的なのは命名です。岩井克人だって三浦雅士だって自分で名乗っているわけじゃなくて、そういう名前が与えられていたわけです。名前は与えられるわけで、それがまさに個人なのです。
―その仕組み自体が法人の仕組みですよ。
岩井 自然人と言われているものも基本的には法人なんです。子どもは違うかもしれませんが。
―いや、すべての人間が物理的かつ社会的、つまり法人ですよ。言語・法・貨幣という社会的実体を認めなければ人間は生きていけないということは、つまり法人としての側面をもたなければ生きていけないということでしょう。
岩井 ええ。その話と市民社会の話をつなげたいと考えているのですけれどね。
岩井 『貨幣論』のなかで、貨幣論の構造と、木村敏の精神病理論とを対応させたのですが、人間の精神病理のあり方は経済の病理のあり方とそっくりなのです。社会的承認の欠如からうまれる病理とは、精神病理でいえば、たとえば鬱病の問題です。経済では、モノが貨幣によって買われないことによって惹き起こされる恐慌です。だけど、分裂病、最近では統合失調症と言わなければならなくなったみたいですが、統合失調症の場合は、これはハイパーインフレーションと同型です。たとえば、宇宙から指令を受けている、というような妄想が出てきたりするわけです。社会による承認が問題となるのではなくて、言葉が体現している社会そのものの自明性が解体してしまう。それが、自分自身が他人に支配されてしまうという妄想として表現されるわけです。言語・法・貨幣がまさに人間性の中心に存在しているのだけれど、その中心性にじつは実体的な根拠がないということを、人格的な次元で具体的に現象してしまう。それが統合失調症で、たぶん脳のケミカルな問題がそうさせるのだと思います。(p.278)
岩井 最近の、第三の社会領域として市民社会をとらえる議論にかんしては、それが市民社会を、自己完結性をもった社会、場合によっては、国家をも資本主義をも超越した社会としてとらえているとしたら、少し違うのではないかと思います。市民社会とは、基本的には、国家か資本主義のどちらかを補完する社会としてとらえるべきだと思っているのです。カントやヘーゲル的な考え方の基本は、人間は尊厳をもった存在として扱われなければならないということです。理性を持った人間は、まさに自分で自分の目的を設定できる存在であることによって、手段としてのみ扱われてはならないということ。モノとしてだけでなく、尊厳ある存在として扱われなければならないということです。お互いの尊厳がお互いに承認され、国家がそれをきちんと保証するということになって、その尊厳の承認が法的な権利というかたちをとる。法律ができれば、たとえば、尊厳をもって扱われなかった場合は、権利が侵害されたとして裁判所に訴えることができるようになる。つまり、このような国家による法的権利が確立していない状態において、人間がお互いに尊厳をもった存在として遇し遇されるということをつねに問題にしつづける場が、まさにぼくの言う市民社会なのですね。それがきちんと確定すると法治国家になる。資本主義についてはうまい言葉が思いつかないんですが。
(三浦)企業かもしれないですね。それこそ法人というか。国家において法にあたるのが資本主義において貨幣であるとすれば、その仕組みそのものでしょうね。(pp.287-288)
岩井 ぼくの研究テーマはもともと貨幣を基盤とした資本主義がいかに本質的矛盾を抱えているかということです。たとえば不均衡動学では、もし市場経済において価格が伸縮的であれば、累積的な不均衡が起きてしまう。市場経済の安定性を確保するためには、利潤原理によって動かされないなんらかの非市場的制度による歯止めが必要になるということを示しています。しかも、いま考えている会社論では、資本主義活動の中心にある株式会社というものが、まさに法人であるということによって、そのコントロールには経営者を必要とし、その経営者には信任というかたちで倫理的行動が要請されているということが主張されているわけです。つまり、ほんらい自己利益の追求が公共の利益を実現するはずの資本主義のど真んなかに、じつは倫理性とでもよぶべきものがなければならないということです。(p.291)
岩井 言語・法・貨幣に対応する市民社会・国家・資本主義という三角形モデルのなかで、国家と資本主義は安定しているように見えるけれども、じつはそれらの基盤をなしている法と貨幣は、ともに自己循環論法によって成立しているわけだから、実体的な根拠を欠いており、つねに自己崩壊してしまう可能性をもっている。言い換えれば、本来的な不安定性をかかえているということをおさえておかなければならない。不安定だからこそ、国家にも資本主義にも完全には還元されない第三の人間活動の領域としての市民社会を必要としている。市民社会的な部分が消えてしまうと、国家も資本主義もそれ自身が本質的に抱えている不安定性、矛盾によって自己崩壊してしまうことになる。その意味で、市民社会とは、国家にも資本主義にも還元されえないことによって、まさに国家と資本主義を補完するということになるのだと思います。市民社会的な部分があることによって、これは具体的に何を指すのかは難しいのだけれども、国家も資本主義もその矛盾をカバーしてもらわなければならないという論理ですね。(pp.291-292)
岩井 だから、法というのはまさしく自己循環論法なので、直接民主政となると悲劇です。専制政治も悪いけれど、すべてを国民投票の押しボタンで決めるというのはもっと悪いシステムです。
(三浦)結局は集団ヒステリーになる。
岩井 そう。だから最後に憲法があるということは、押しボタン制にしない、国民投票にかけないということです。(p.292)
岩井 株主主権論が少しでも意味をもつとしたら、まさにこのような株式市場の公共性を前提として、内向きの経営をしがちな経営者に対して、株式市場の声に耳を傾けろと叱咤激励するわけです。ところが、株主主権論をもっとも声高に主張していた人間(堀江さんと村上さん)が、株式市場の公共性を裏切ってしまうインサイダー取引をしていたというのは、弁護の余地はない。
(略)
…ぼくの会社論は、株主主権論を理論的に批判しているわけです。法人化されていない八百屋さんのような古典的な個人企業と、法人化された株式会社を混同した理論的な誤謬であると、批判してきたわけです。だから、堀江さんと村上さんにはちゃんとしてもらわなければ困るわけですよ。相手が、法律違反で負けてしまっては、理論的な戦いが成立しなくなってしまう。(pp.294-295)
岩井 (孫正義さんは金儲けから会社を育てるほうによく転換したという話の流れで)日本人はお金がそんなに好きじゃない。好きだとしても、それよりは社会的認知のほうが気になるムラ的な人たちなんだと思う。そこでみんな引っ掛かっちゃう。(p.296)
(三浦)それと同時に、やはり先ほどの大義名分もあるんじゃないですか。日本人はとくにそうかもしれませんが、世界的にもやはり冒険と金儲けだけではない。どんな会社でも、感謝、勤勉、奉仕とか掲げている。逆に言うと、それがなければ、社員が働かない。俺たちは金儲けのためだけに邁進しているというのでは働かない。岩井さんのおっしゃる市民社会的な理念というのを表向きであれ掲げなければやっていけないというところがある。極論すれば、すべての企業がノン・プロフィット・オーガニゼーションみたいなところがあるわけです。(略)
岩井 そうそう。だが、それがぼくの言う市民社会かどうかは疑問ですが。
(三浦)でも、たいていの会社は、社会のためにこの会社は設立されたとか言っているでしょう。
岩井 ええ。定款にもかならず書いてある。
(三浦)定款に「万難を排して金儲けに邁進する」と書いてある企業はない(笑)。なんらかのかたちで社会に貢献する、となっている。
岩井 シニカルに見ればそれは方便なんでしょうけど、同時に方便だけじゃないと思いますね。
(三浦)方便じゃないと思います。労働者も法人の面をもっていますから。家に帰れば夫であり、お父さんであり、会社の外には学生時代の友人もいる。敬意を払われたいという欲望はつねにあるわけだから、大義名分がなければやっていけない。
(p.297-298)
岩井 ただ、ぼくがいまやっている研究は、もう少しテクニカルな研究です。最近、経済学の影響で、人間と人間とのあいだの法的な関係も、すべて契約関係か疑似契約関係に還元しようという動きが、法学のなかでも強くなってきています。契約関係とは、基本的には、自己利益追求が基本原理です。自分の利益にならなければ、だれも契約を結ぶことを強制されません。契約自由の原則とも言われます。だが、じつは、そのような契約関係に還元することのできない人間関係がたくさんあるということを、ぼくは言おうとしているのです。
最初の研究は、法人としての会社とその経営者との関係を分析することから出発したのですが、その後、財団法人とその理事との関係、国民と国家官僚との関係、患者と医者との関係、支配株主と少数株主との関係、子どもや認知症老人とその後見人との関係、皿には、未来世代と現在世代との関係、などなど、まさに一大領域を成していることに気がつくことになりました。これらの関係には、たとえば医者は患者の病状にかんしては、患者自身よりもよく知りうる立場にあるというふうに、絶対的な非対称性があります。そこで、この関係を契約関係として結ぼうとすると、いくらインフォームド・コンセントと言っても、医者の一方的な自己契約になってしまう可能性がつねにあります。自己契約は、契約にはなりえないというのが、法律上の大原則です。事実、最悪の場合は、契約の名のもとに、2004年の慈恵医大青戸病院事件のように、医者が患者を人体実験に使ってしまうこともありうるのです。そうすると、この患者と医者との関係を望ましいものに維持していくためには、自己利益追求を前提とする契約関係と異なり、医者の側に、患者のために治療すべしという倫理的な義務を一方的に課すことが必要になってくる。それが、信任関係といわれるもので、それにかんする法律を信任法といいます。このようにして、法の世界のなかにも、市民社会的な原理が絶対的に必要とされるという議論を展開しようとしています。(pp.299-300)
(三浦)イスラム原理主義はアメリカのキリスト教原理主義の模倣だという説がありますね。
岩井 ええ。何度も同じことを繰り返しますが、国家も資本主義も、つねに危機を内にかかえています。法も、貨幣も、自己循環論法であるがゆえに、それ自身に自己崩壊のモードを内包している。それらは市民社会につながることでまがりなりにも維持されているのです。これまでは貨幣の側から倫理性の必要を示してきたわけですが、いまは法の側から倫理性の必要を示そうとしています。それが終わったら、今度は逆に、市民社会の側から考察をまとめてみたいと思っているわけです。(p.301)
岩井 まさにそうです。人間は根拠がないことを恐がります。自己循環論法から逃げ出そうとして、なんらかの実体をもとめてしまう。貨幣の背後に金をもとめ、労働をもとめ、極端な場合は糞尿愛をもとめる。あるいは、貨幣のような媒介を排除して、透明で直接的な人間関係なるものをもとめる社会主義や共同体主義になってしまい、まさに人間の自由をもっとも抑圧する体制を生み出してしまうわけです。国の場合であれば、宗教や民族性をもとめてしまうわけですね。(p.302)
岩井 カントの倫理論の中心には、いま三浦さんが述べられた「定言命題」があります。サンデルも解説していますが、カント以外の倫理論や正義論は、基本的には、最大多数の最大幸福のために何々をせよとか、共同体の善を促進するために何々をせよとかいった「仮言命題」として提示されています。
だが、そのような倫理はあくまでも何らかの目的の手段でしかなく、その目的の設定には必然的に人間や社会に関する経験論的な判断を必要とします。これに対して、定言命題は法や倫理を幸福や善といった外的な目的から切り離す。そのひとつの定式は「あなたの行動の原理が同時にすべての人間にとっての普遍的な法として成立するように行動せよ」というものです。まさに経験的な世界から独立した、純粋に形式的な命令となっている。 (略)
まさにいま、無縁性などよりもはるかに根源的な無根拠性の問題に直面している。それだからこそ、共同体的存在としての人間をとりまくさまざまな条件とは独立した、まさに純粋に形式性としての倫理の可能性について考える意味があると思います。そして、それは同時に、物理的な条件にも生物的な条件にも還元できない人間の本質とは何かを考えることでもあるわけですね。(pp.310-311)
****
引用は以上です。
いかがでしたか。
2006年の時点で既に、生物学者と議論して「遺伝子決定論」で確定だと言っているくだり、着眼の速さに脱帽です。また、引用部分にはなかったかもしれませんが、「承認が極端に欠乏すれば精神疾患になる」ということをあっさり言っています。これも不肖正田が『承認をめぐる病』という本に触れて言ったことと一緒ですね。
「日本人はお金がそんなに好きじゃない」
この言葉も至極あっさりと出てきます。某「学力本」のうさん臭さに気がついたわれわれは、耳を傾けたいですね。
そして、「信任関係」のくだり。
医者と患者との間には、情報の「絶対的な非対称性がある」、だからこそ「医者の側に、患者のために治療すべしという倫理的な義務を一方的に課すことが必要になってくる」。
このところ「学者が目立ちたい一心で正しくないことを言ってしまう」という現象が引きも切らなかったわけですが、ここにも、本来は「信任関係」が存在すべきところなのではないでしょうか。「学者と一般人」の関係性のなかには「情報の絶対的な非対称性」があります。であれば、本来学者は間違ったことを言ってはならないのです、わたしの解釈によれば。自分の肩書を、間違ったことを言って本を売るための手段として使う学者が多すぎます。
いみじくも、昨12月このブログで批判的にとりあげた 『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』(日経BP社)の著者、入山章栄氏は、「役に立つかどうかよりも、『おもしろいか、おもしろくないか』が僕の最大の価値基準ですね。」ということを述べていますが、
http://diamond.jp/articles/-/82877?page=2
これは考えてみると恐るべきことで、入山氏の著作で「ダイバーシティー経営」に関してわたしが引っかかった箇所、
「ほとんど男性でできている日本企業に女性を雇う必要はない」
この、当事者にとっては極めてセンシティブな内容の発言も、入山氏は「おもしろいから」もっというと「面白半分で」言っている可能性があるのですね。
つまり、このへんの「ザコ学者」と「大学者」の言うことの価値には天と地ほどの開きがあり、われわれ一般人は、ごく少数の「大学者」の言うことには耳を傾ける必要があるが、大多数の「ザコ学者」―たとえ東大出でも、海外で博士号をとってきたのでも―は、「正しくない」あるいは「言葉の軽い」人であり、無視してよい、と理解してよいと思います。
というふうにすぐ我田引水的に解釈を施してしまいますが、新年のお口直しに、大きな知性に触れるために、お勧めの1冊です。
正田佐与

コメント